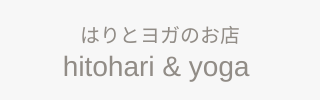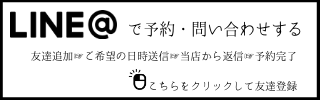2025-10-03
突発性難聴と鼻・喉の関わりについて
目次
鼻と喉のトラブルが耳に響くとき
—「鼻づまりのあと耳がこもる」その背景と、整え方のヒント—
朝起きて鼻がつまって、のども少しイガイガ。そんな日に限って「耳がふわっと詰まる」「低い音だけ聞き取りづらい」。
施術室でもよく出る相談です。
耳の症状は“耳だけの問題”に見えますが、鼻や喉(上気道)の状態に左右されやすいのが現実。今日はそのつながりを、できるだけやさしく書いてみます。
鼻・喉と耳は、細いトンネルでつながっている
耳の奥には耳管(じかん)という細い管があり、鼻の奥(上咽頭)へ続いています。
鼻炎・副鼻腔炎・風邪明け・後鼻漏、あるいは長引く咽頭の緊張や口呼吸があると、この耳管の働きが鈍って耳の圧が抜けにくい=こもる・詰まる・聞こえにくいが起きやすくなります。
自律神経が乱れていると耳管周囲の粘膜や筋の動きも固くなり、「良いときと悪いときの差」が出やすくなるのも特徴です。
よくあるお声
•鼻づまりのあと耳が詰まった感じが続く
•風邪・花粉症のあと耳鳴りが強くなった
•低音だけ聞き取りづらい/声や環境音がこもる
•**のどの違和感(異物感)**が続き、同時に耳も不快
•治療を受けているが**「異常なし」なのに辛い**
•ときどきめまいやふらつきも重なる
※急に聞こえが落ちた/回転性の強いめまい/激しい耳痛や発熱…は、まず耳鼻咽喉科へ。医療の受診が最優先です。
どうして鼻・喉が整うと耳がラクになるのか
•圧の換気:耳管が開きやすくなり、中耳の圧が整う
•粘膜のむくみ軽減:鼻~上咽頭の炎症・浮腫が引く
•筋の緊張低下:咽頭・胸鎖乳突筋・肩甲帯のこわばりがほどけ、耳管周囲が動きやすくなる
•自律神経の安定:交感神経優位(緊張モード)が続くと症状がぶり返しやすいので、睡眠と呼吸の質を底上げすることが土台づくりになります
鍼灸でお手伝いできること
hitohariでは、鼻や喉そのものをグイグイ触るよりも、手足のツボ・背中や胸まわり・首すじから整えていくことが多いです。
•鼻・上咽頭のむくみを和らげるツボ(手・足)
•首前~側(胸鎖乳突筋)・肩甲帯の緊張緩和
•胸郭をゆるめて鼻呼吸がしやすい姿勢づくり
•迷走神経系を意識した施術で自律神経の安定を後押し
薬で変化が乏しかった方でも、「耳のこもりが抜けやすい日が増えた」「耳鳴りの不快感が下がった」と感じるきっかけになることがあります。※効果には個人差があります。
今日はここだけ意識してみるセルフケア
1.やさしい鼻うがい/温蒸気
ぬるま湯+専用塩で刺激少なく。就寝前の加湿も◎。
2.口を閉じて“鼻から吸う・長く吐く”
4秒吸って6〜8秒吐くを数回。のどの力みを抜いて。
3.舌先は上顎の前歯の付け根に添える
口呼吸になりにくく、耳管周りの緊張が和らぎます。
4.カフェイン・アルコールは控えめに
粘膜の乾燥と睡眠の質低下を避けるため。
受診の目安
•突然の聴力低下、強いめまい、激しい耳痛・発熱
•片側だけの耳の閉塞感や耳鳴りが急に悪化
•数週間セルフケアをしても改善が見られない
こうした場合は耳鼻咽喉科での評価が最優先です。そのうえで、「治療を続けても戻りやすい」「日常の不快感が残る」場面こそ、鍼灸で回復しやすい土台づくりを並走できます。
よくいただく質問
Q:耳鳴りやこもりは“治りますか”?
A:一律には言えません。ただ、鼻・喉・首肩・自律神経を含めた“全体の負担”を減らすと、強さ・頻度・不快感が下がるケースは少なくありません。
Q:どれくらいのペースが目安?
A:急な悪化直後は短めの間隔で、落ち着いてきたら間隔をあけて維持。生活リズム(睡眠・呼吸)とセットで整えるのがコツです。
まとめ
鼻や喉の不調は、耳のこもり・耳鳴り・聞こえにくさに静かに影響します。
「異常なし」と言われても辛い――そんなときは、耳だけに焦点を当てすぎず、鼻・喉・首肩・自律神経まで含めて整える戦略が遠回りに見えて近道です。
不安なときは、一人で抱え込まずにご相談ください。ていねいに耳を澄ませながら、回復の道筋を一緒に探していきます。
💡さらに詳しく知りたい方は、突発性難聴に関するコラム一覧 をご覧ください。
一人で悩まずに、ますはご相談ください。
こちらからご予約いただけます。
関連記事